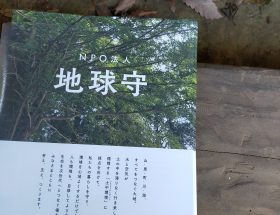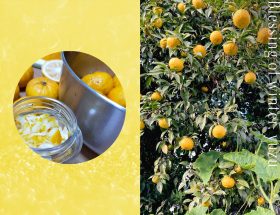「土器で炊いた野菜を食べれる店がある」と聞いて、神楽坂の「さいめ」という料理屋に伺った。
窓がふさがれた店の前に立った時、開放感のある屋内が好きなわたしは「洞窟のような店内は苦手だけど・・」と少し構えた。
入ってみると、見慣れない調理場と、不思議な安堵感があった。そして想像より若い店主。
コンロのようなものは、土で出来ているように見える。同じような素材で、見慣れない筒状の台もある。上に換気扇と思われるものがあるから、こちらも火元だろうか・・?
安堵感はおそらく、店内に並べられたたくさんの丸っこい土器と、土でできた火元のせいだろう。皆素朴で息づかいがあるように感じられる。
席に座って最初に聞かれたのは、「手でいいですか?箸を使いますか?」というものだった。手・・!と驚いていると、夫が「手で」と返事をした。
瑞々しさと焼き目が同居する野菜たち
調理場を見ると、店主も手で調理している(驚)。箸は使わず、聞けば火鉢だというその上で、手で野菜を転がしている。
「素手は不衛生だから料理動画を撮るときはビニール手袋を」という指南に浸かっていた私は、先日の出来事も合間って、この時なにか価値観がリセットされるのを感じた。
一品目に出てきたのは、輪切りにされたカボチャだった。
おもむろに手で掴み、口元に近づけると、いい香りが漂ってくる。何の香りだろう・・?と思いながらカボチャを口にする。歯ごたえがある、皮付きだから・・? 硬い部分と、カボチャのほくほくとした感じ、蒸し野菜のような瑞々しさ、焼き目の香ばしさ・・
聞けば、この蒸し野菜のような感じだけど焼き目が付くというのが、土器ならではの炊き上がりらしい。水分を飛ばす焼くという行為、水分を入れる煮るという行為。その両方を含むような土器。
二品目はピンク色の蕪。大きい!
自分ではこんなに大きく切って調理したことは無い。大きいだけで贅沢な感じがする。けれど、家で真似をしてもこの贅沢さは出ない気がする。土器や空間や時間が、この贅沢さを作るために一役買っているのを知らされる。
かぶりつくと、水分がしたたるほどのジューシーさ。聞けば細かく切るほど水分は飛んでしまうが、大きく切ると水分を保有しやすいらしい。あたたかく、みずみずしく、香ばしい。寒い冬に食べたい調理法。だんだん土器が欲しくなってくる・・。
三品目は葱。食べやすい大きさに切られた葱しか知らなかったが、この時出てきたのは、葱一本を三等分にしたうちの2つ分、という感じの大きさ。手で掴んでかじりつく。あまい・・。知らなかった葱の新たな一面が引き出されている。「本来のおいしさ」というようなものと、「グルメ」のようなものの、中間のような感覚。野菜を知るほどに、料理というのは土がしている、人はそれを頂くだけ・・という感覚になっていたが、収穫された野菜に人が手を施すということの、調味とは違う、意義のような何かを感じる。
四品目はさつまいも。大好きなさつまいも・・。かぶりつくと中は紫色。土器ならではの香ばしさとみずみずしさを備えたスイートポテトを味わう。
五品目は里芋。ここに来て写真を撮ってみる。

「このタイミングでですか?今までの野菜の方が見た目のインパクトあるのに」と笑われる。ころんとした様子が可愛らしかった。
ごつごつした見た目から、なぜか里芋の皮は剥かなければいけないと思っていた。初めて食べる皮付きの里芋。かりじつくと、雪のように真っ白に澄んだ実があらわれる。白が好きで、でも自然界にあるのは生成りのような白、漂白したような白さは無いな・・と思っていた時期もあったが、心踊るような白が、ごつごつとした皮の中に詰まっていた。

複雑な皮目の舌触りと、皮からつるんと剥がれていく里芋の独特の舌触り。これからは家でも皮付きで食べよう。
六品目、「うちのメインディッシュです」と冗談まじりに出てきたのは豆たち。コースを通じてあった香ばしさと瑞々しさが、小さい一粒一粒にも宿っている。
「無限にいけますね」と話しながら、最後の一粒まで美味しくいただく。
素材との出会い 人との出会い
豆を食べ終わり、塩を単独でつまんでみた。塩は結晶だということがわかるような、大きな結晶の塩。
聞けばフランスのベルトンヌという地域で作られている塩らしい。
旅の中で出会ったその塩は、廃れそうな昔ながらの製法を、その塩を気に入った若者三人が「こんな塩が受け継がれないなんて」と自分たちで作るようになったらしい。塩を作るのは気候や湿度などが整ったわずかな期間で、それ以外は、そのわずかな期間のために塩田や建物の整備をしたりして過ごすらしい。
「自分にはそんなにわからないですけど、気のいい場所でした」と店主がその地のことを教えてくれた。ほわほわするような、と。自然の地形に沿った塩田。いつかきっと行こうと心に記す。
お店ではお酒も出している。焼酎、赤ワイン、はちみつのお酒、シードル。
「芋そのものの香りがする焼酎、農薬が苦味につながる、この焼酎はそれが無い、ほぼ農家のような作り手が作る焼酎、高く売らない、ぎりぎり生活出来るか無くなるかという値段の酒」
普段焼酎なんて一切飲まないが、そんな話を聞いて、気になって頼んでみた。二人で一杯。薄めの水割り。焼酎のイメージとは違う、すっきりとした飲みやすさ。
「酒も野菜も人なんですよ」そんなことを話していた。感覚が合う、と選んできた素材たち。通じた人たち。
食事をした2時間、店主と話して、彼は自分の感覚で生き、行動し、言葉にしているような気がした。確信めいた話し方ひとつひとつに、お腹いっぱいになる感覚もあった。彼から発せられるエネルギーと同等のエネルギーを返すのが疲れると感じた。帰り道に夫にそんなことを話していると、「それはこちらに向き合っているということ」と返ってきた。それは、彼が彼の感覚に従っているからだと思った、そして、わたしはどれだけ自分の感覚で生きてるだろうかと思った。
例えば「一物全体」という考え方と出会い、それを話す人々と出会い、今日も皮付きの野菜たちを食べて、一物全体という考え方は、わたしにとってしっくりくる考え方になっている。けれど一物全体について話そうとする時、本に記された言葉を話す以外に、わたしは何か話せるだろうかと疑問が生まれた。
理論立てて説明する必要はない。一物全体という言葉に集約される必要もない。自分の感覚を形にしてみる、言葉にしてみるということに興味がわいた夜となった。
神楽坂 さいめ https://www.saime.jp/